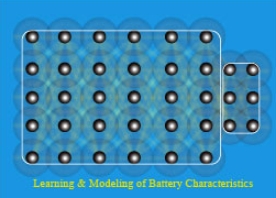
2050年カーボンニュートラルに向けて、太陽光発電や風力発電など変動性再生可能エネルギー(VRE: Variable Renewable Energy)電力系統への導入が急速に拡大しています。一方、VREの課題が顕在化してきています。例えば日本では新エネルギー*1における太陽光発電の導入割合が世界主要各国と比べて非常に高い水準です*2。その結果、空調需要の少ない春や秋の昼間に太陽光発電余剰電力が生じたり、あるいは悪天候で寒い日に電力逼迫の状況となったりしています。
*1 (一社)新エネルギー財団サイト
*2 IRENA, Renewable Capacity Statistics 2022
そこで昼間の余剰電力を一時的に充電し、夕方の電力需要が高まる時間帯に放電するなどして、電力需給のアンバランスを解消する事が求められています。その手段として各種蓄電池が注目されており、有力な候補の一つは電気自動車等で使われるリチウムイオン電池です。現在この分野で検討されている蓄電池の活用方法は、一需要家による独自利用ではなく、電力エネルギーネットワークに接続し複数の事業で共用する形態です*3。この場合、多数の蓄電池がIoTで仮想的に束ねられ有機的・知的に運用されることになります。これはいわゆる仮想発電所あるいはエネルギー・リソース・アグリゲーションの一部ですが、蓄電池とそのネットワークだけを指してバッテリーアグリゲーション*4またはクラウドバッテリーマネジメントシステム*5と呼ばれた事例があります。
*3 経済産業省 第3回蓄電池産業戦略検討官民協議会 資料3
*4 2013 IEEE Grenoble Conference Proceedings
*5 J. Energy Storage, vol.30, 101557, 2020.
このような蓄電池活用では、過去の活用方法と比較して電池容量が非常に大きくなるため、充放電エネルギー効率の重要性が高まります*6。充放電エネルギー効率はRTE(Round Trip Efficiency)とも呼ばれます*7。一般的なRTEの値としてリチウムイオン電池の単電池は95%、その蓄電システムとしては86%が知られています*8。ただしこれらは新品かつ一定の条件(充放電電流や温度など)における値であることに注意が必要です。リチウムイオン電池は劣化によってRTEが低下する性質を持っています*9。劣化によりRTEが低下する現象は効率劣化(Efficiency Degradation)と呼ばれ、この効率劣化は先に述べた電力需給のアンバランス解消の運用において、エネルギー損失の形で影響を及ぼします。エネルギー損失が大きくなると、再生可能エネルギー利用効率や運用経済性の低下につながります。
*6 Sustain. Energy Fuels, vol.1, no.10, pp.2053-2060, 2017.
*7 Appl. Energy, vol.210, no.15, pp.211-229, 2018.
*8 JEC-TR-59002:2018
*9 IEEE Trans. Ind. Appl., vol.55, no.2, pp.1932-1940, 2019.
また、リチウムイオン電池のRTEに関しては、昨今のリユース電池の導入拡大を考慮する必要があります。リチウムイオン電池は従来正極活物質に使用されてきたコバルトやニッケルなどのレアメタルを使用回避する技術が相当に発展してきていますが、原理的に電池容量あたりのリチウムの使用を回避することができません。これは、全固体リチウムイオン電池やリチウム金属電池などの先進的な電池でも同様です。現在リチウムは世界で1×105純分t/年 程度の生産量があります*10が、仮に世界の自動車(約9000万台/年 の生産量)が全て電気自動車(平均100kWh)に置き換わったとすると、9TWh/年 程度のリチウムイオン電池が必要になり、そのために必要なリチウムは当量計算上、約6.5×105純分t/年 になります。もちろんリチウムの増産は進められていますが、2020年代中頃からのリチウム需給逼迫が予想されており*11、そのため車載リチウムイオン電池のリユース・リサイクルの取組みが活発化してきています。最近では、リユースに関する規格や認証の策定が活発化しています*12-15。
*10 JOGMEC 鉱物資源マテリアルフロー
*11 経済産業省 第2回蓄電池産業戦略官民協議会 資料3
*12 JIS Q9092:2022
*13 JETリユース電池認証
*14 UL 1974
*15 IEC 63330
リユース電池は主に様々な条件で運用され劣化した車載リチウムイオン電池です。出入力特性の低下は進んでいるものの、温和な充放電条件で使用する場合の電池容量低下がそれほどでもない点に注目し、用途を車載用から定置用に変えて再利用します。一方、出入力特性とRTEはともに電池の内部抵抗と関係があり、従ってリユース電池は同種電池の新品と比較してRTEが低くなります。そして、リユース電池の劣化度や、運用中の劣化進展が様々であることが相乗的に作用し、定置用リチウムイオン電池のアグリゲーションでは、個々の電池のRTEが非常に多岐にわたると予想されます。この状況において電気を効率的・経済的に運用するためには、各々の電池のRTEをリアルタイムに把握する技術が不可欠であると考えました。
そこで、リチウムイオン電池のRTEを把握するための手法として、私たちは効率劣化診断技術を研究開発しております。
なおご参考までに、この効率劣化診断に関連する主な報文・著書(単著・共著含む)は以下の通りです。
① エネルギー・資源学会論文誌, vol.39, no.3, pp.11-20, 2018.
② ICCEーBerlin 2019 Proceedings.
③ 電子情報通信学会和文論文誌B, vol.J104-B, no.3, pp.232-241, 2021.
④ リチウムイオン蓄電池の効率劣化診断の研究 (博士学位論文)
⑤ スマートグリッドと蓄電技術 (書籍)
⑥ Sensors, vol.22, no.14, 5156, 2022.
⑦ 電気学会論文誌C, vol.142, no.8, pp.832-839, 2022.
蓄電池劣化診断・経済性推定に関するお客様からよくいただくご質問とその回答をまとめております。
Q
他の劣化診断と大和製罐の劣化診断はどこが違うのですか?
A
現在報告されている劣化診断のほとんどは、蓄電池の満充電容量または内部抵抗を診断してその健全性を判定するものであり、蓄電池の残価設定などへの応用が期待されています。これに対し当社の劣化診断は蓄電池の充放電特性をモデル化してさまざまな充放電条件でのエネルギー効率を推定するものであり、クラウドバッテリー(アグリゲートされた蓄電池)の運用経済性最適化などへの応用が期待されます。
Q
大和製罐の劣化診断研究開発はどのような状況ですか?
A
現在、大学や他企業と協力しながら劣化診断手法の基礎・応用検討および実証試験を進めています。これらの検討内容は公開可能なもの限定ではありますが、国内外の学会および論文で発表していきます。また発表内容やその関連情報については本ホームページにて順次情報提供していきます。
FFT(高速フーリエ変換)アナライザやFRA(周波数特性分析器)による交流インピ...
これまで、リチウムイオン電池の劣化現象として ・容量劣化(満充電容量の低下。SO...
※「リチウムイオン電池の劣化診断」については、コラム第14回(リチウムイオン電池...
3月16~18日に開催されました平成28年電気学会全国大会(東北大)にて、弊社よ...