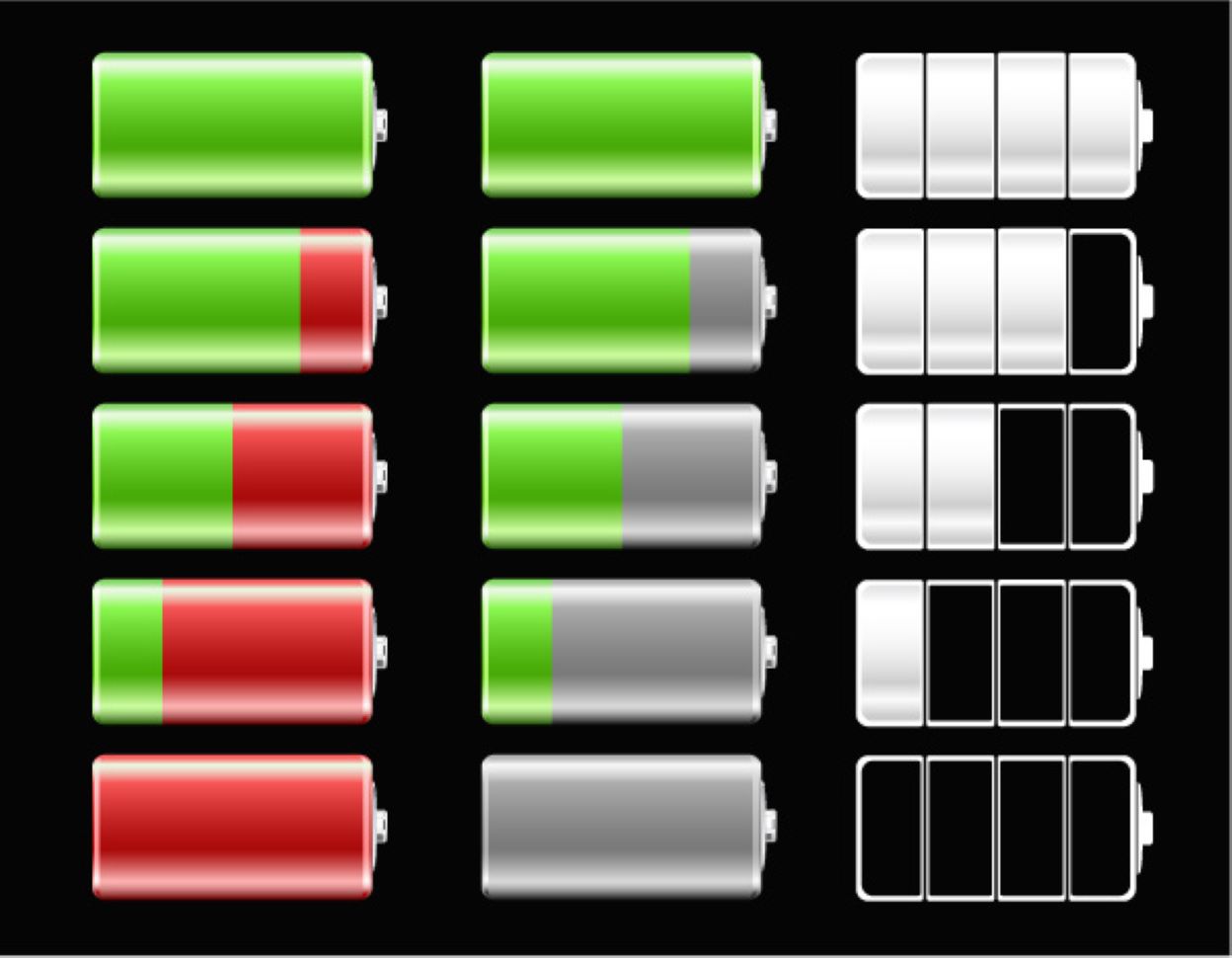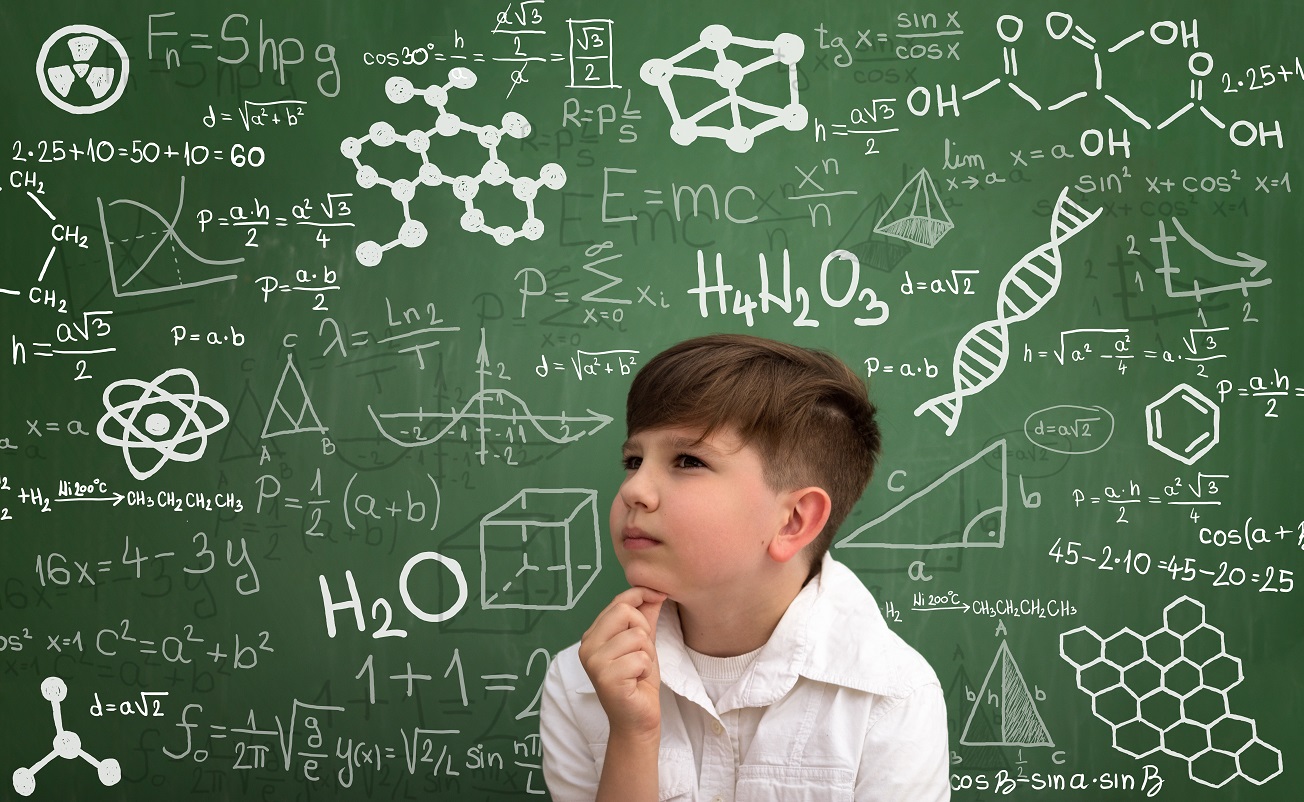
こんにちは。今回はしばらく続けていた話題と少し違う角度から話をしたいと思います。
筆者はいわゆる化学屋だと勝手ながら自負してきました。学生時代には有機化学の研究をし、就職後は機器分析によるリチウムイオン電池評価に携わって、ずっと化学を拠り所に仕事をしてきたからです。もちろん、数々の偉大な諸先生方の功績を前に化学屋を自称して良いのかという、ある種の葛藤は常に付きまとうのですが・・・。
さて、化学屋の話はわかりにくい、とよく言われます。当然、話し手の説明力不足もあると思いますが、それだけではなくどうやら聞き手と話し手の考え方に隔たりがあるのではないか・・・と感じる事があります。例えば「化学反応」に対するイメージの違いが挙げられます。
化学屋でない皆さんは、「化学反応」にどの様なイメージを持っているでしょうか?多分、二つのフラスコの中身を混ぜるとボワっと反応して新しい何かができる、こんなイメージではないでしょうか?
このイメージの反応は、「不可逆な熱力学的反応」と呼ばれるものです。これとは真逆の概念に、「可逆な速度論的反応」というものがあるのですが、化学屋でない人がこの反応をイメージするのは少し厄介かもしれません。
可逆か不可逆か、熱力学的か速度論的かの2元的組合せによって、化学反応は図1の様に4通りの反応パターンに分類できます。
| 逆反応できる (可逆) |
逆反応できない (不可逆) |
|
|---|---|---|
| 生成物が安定的 (熱力学的) |
可逆な熱力学的反応 | 不可逆な熱力学的反応 |
| 生成が速い (速度論的) |
可逆な速度論的反応 | 不可逆な速度論的反応 |
図1.化学反応のパターン
化学屋はこれらを無意識で考えながら話をしているのに対して、化学屋でない人は「不可逆な熱力学的反応」を想像しながら話を聞いてしまう為に、わかりにくい状況が生まれるのではないでしょうか。
ここまでは抽象的な話でしたので、具体的にリチウムイオン電池の充放電反応を使って考えてみましょう。充電は、電池の正負極間に外部から電圧を加えて負極へのリチウムイオン移動速度を高めた結果起こる速度論的な反応です。放電はエネルギー的に安定な正極にリチウムイオンが移動することで起こる熱力学的な反応です。なお充放電は繰り返し行えるので、どちらも可逆です。
また、徐々に電池容量が減少していく劣化反応は、安定的で元に戻らない非可逆で熱力学的な反応だと考えられます。
この様に、リチウムイオン電池の反応にも様々なパターンが含まれています。電池反応を理解するにあたり重要となる概念ですので、化学に縁のない人にも是非知って頂けるよう、今後このコラムを通じて様々な話をしていきたいと思います。