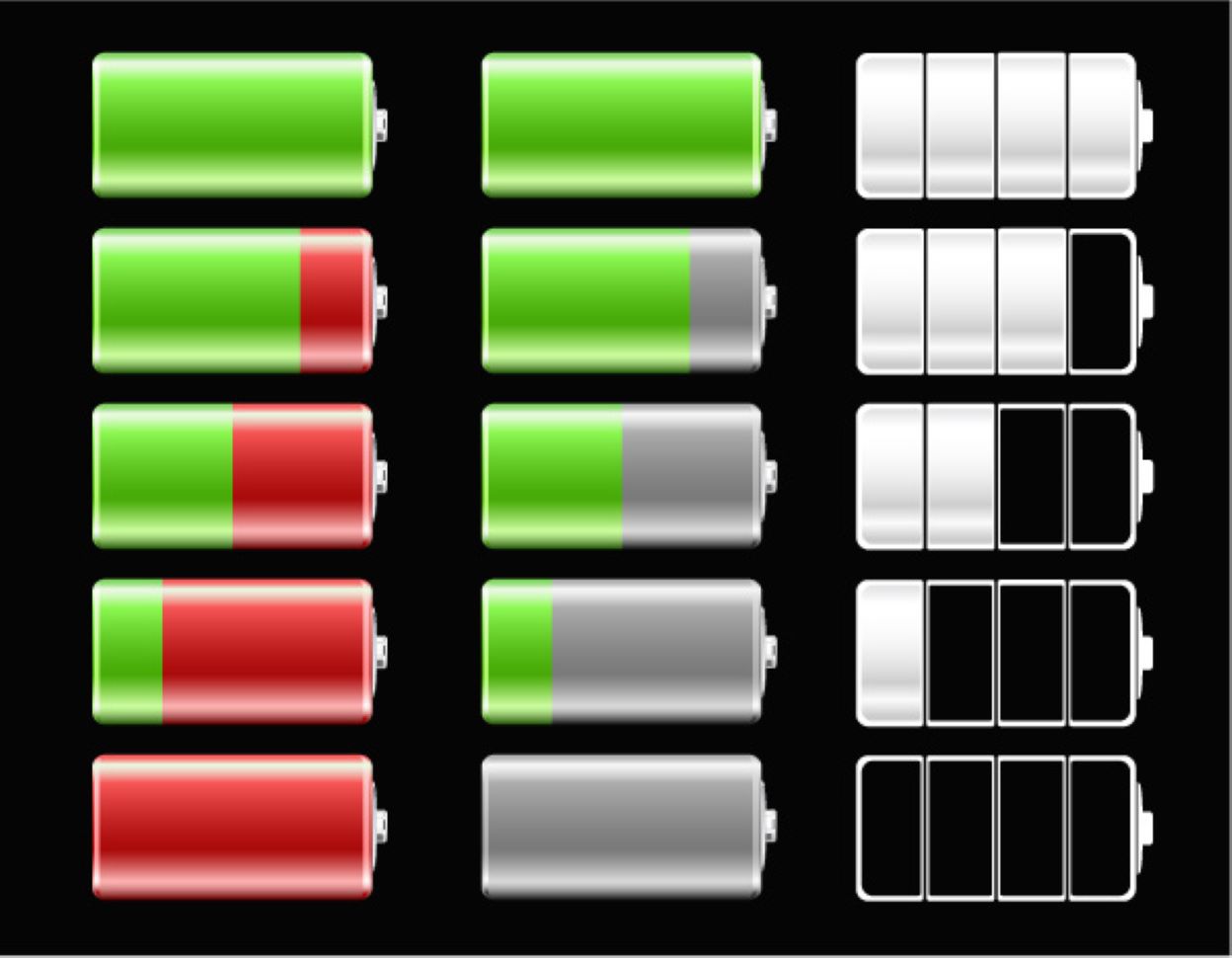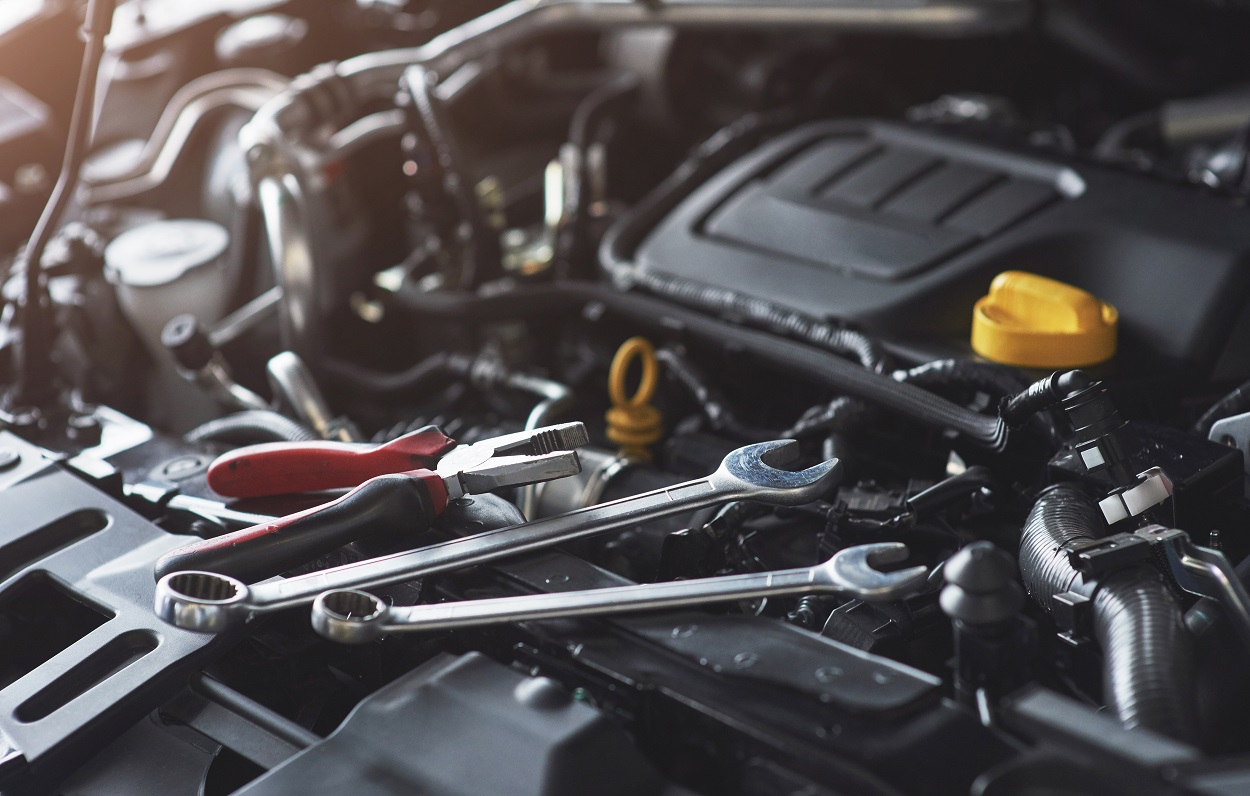
リチウムイオン電池は1990年代前半に登場したあと、2000年代中ごろに小形民生分野で発火事故等が相次ぎ、安全性への懸念がクローズアップされました。
その後に実施された様々な規格制定や電池製造メーカー様の努力によって
- 過充電
- 過放電
- 転極
- 外部短絡
- 内部短絡(電池製造時に混入した異物起因)
による危険が低減され飛躍的に安全性が高まりました。近年ではリチウムイオン電池は大型化し、電気自動車・ハイブリッド自動車・定置用蓄電池等で広く使用されるようになっています。
しかし、リチウムイオン電池は使用中、まれに電池内部でリチウム金属が樹状に析出し内部短絡・発火を引き起こす危険性があります。この現象は電池容量の低下、いわゆる劣化が進行すると発生しやすくなる事が経験的に知られており、これまでは電池容量が60%~80%まで低下した段階を電池の寿命と定義※1することによってこのリチウム金属析出による内部短絡を未然に防止してきました。
最近、電池容量の低下傾向が『ルート則』を外れた時に電池内部でリチウム金属が析出する可能性があることを示唆する研究報告※2がありました。
ルート則とは次の軸のグラフを作成すると直線関係になる、というものです。
- 縦軸:電池容量
- 横軸:電池使用期間、またはサイクル数の平方根
この報告内容を踏まえますと、運用中のリチウムイオン電池について下記の流れでリチウム金属析出の可能性を警告し、バッテリー交換時期を知らせる事ができるかもしれません。
- 使用中のリチウムイオン電池の電池容量低下を常にモニタリングする
- 電池容量の推移をルート則に当てはめ、常に比較する
- 電池容量の推移がルート則から外れたら、リチウム金属析出の警告をする
今後このような取組みがさらに進めば、リチウムイオン電池を今以上に安全に利用できるようになることが期待されます。
※1 たとえばJIS C8711やJIS C8715-1※2 第56回電池討論会 講演番号3M04